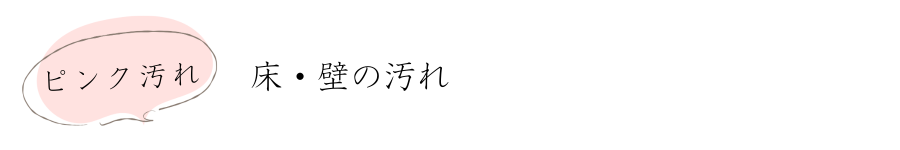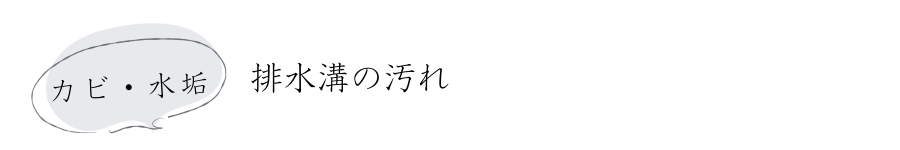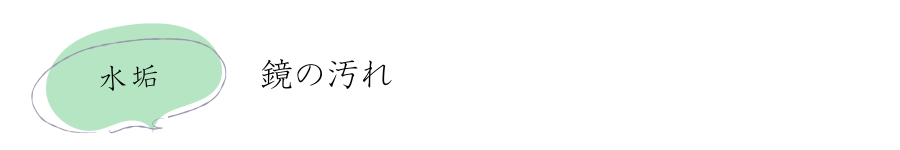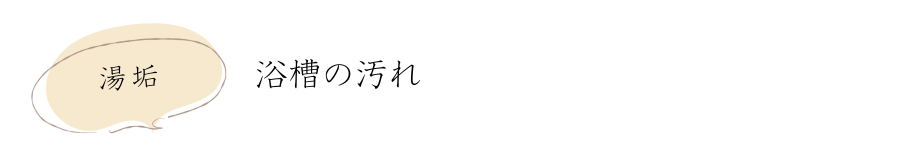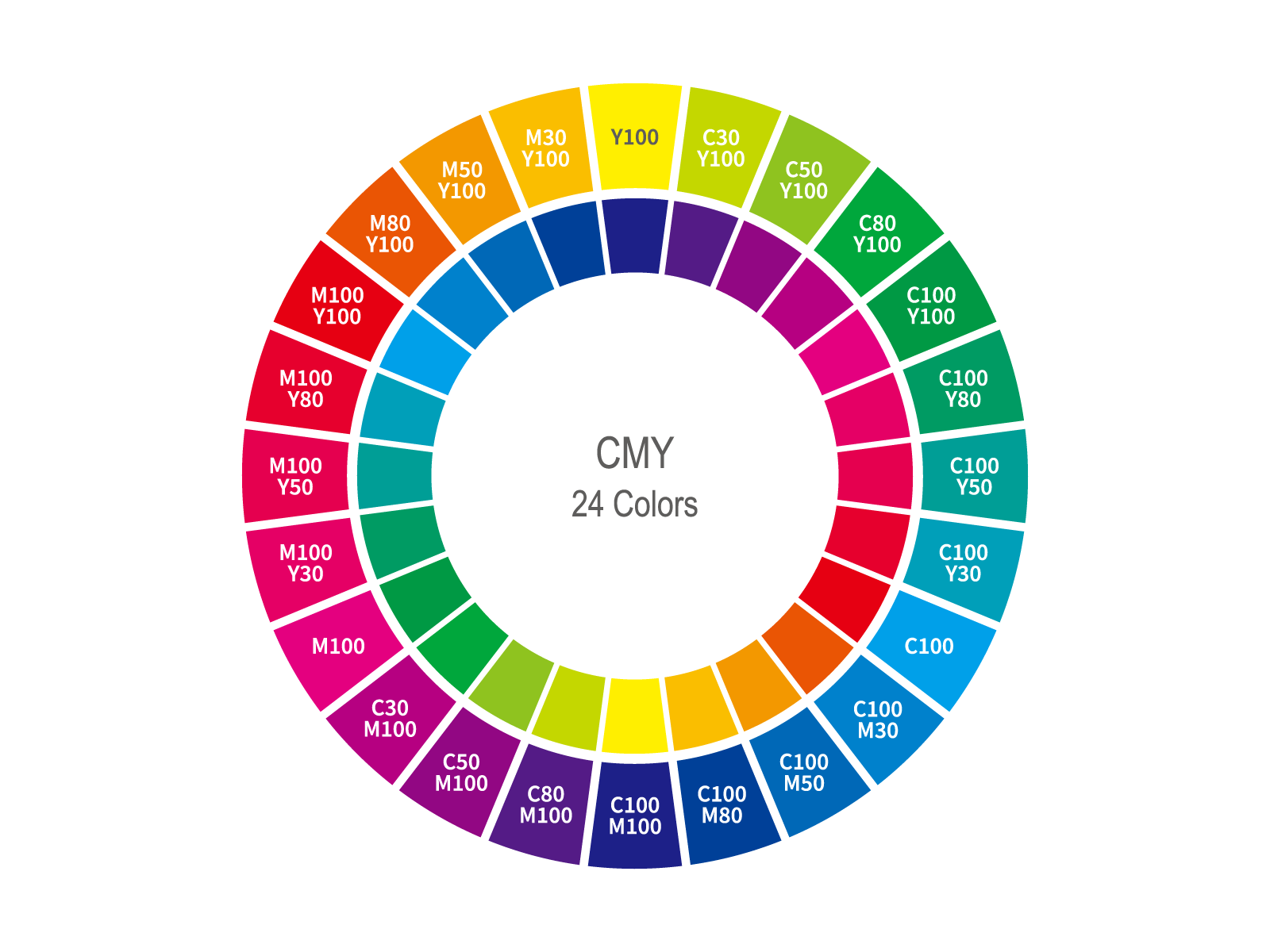クラフトマンワークスの取り組み 通気断熱WB工法
皆様こんにちは。
快適な家づくりを日々研究している峯です。
弊社が取り組んでおります通気断熱WB工法も全国の工務店によって
数々の作り方や材料の違いがあります。
クラフトマンワークスでは、今後紀州材にこだわったWB工法を
ご紹介させていただきます。
ぜひ一度お問い合わせの上、ご来店ください。
和歌山県産木で建てる地産地消の住まいで長く健康で安心なお家をご案内いたします。
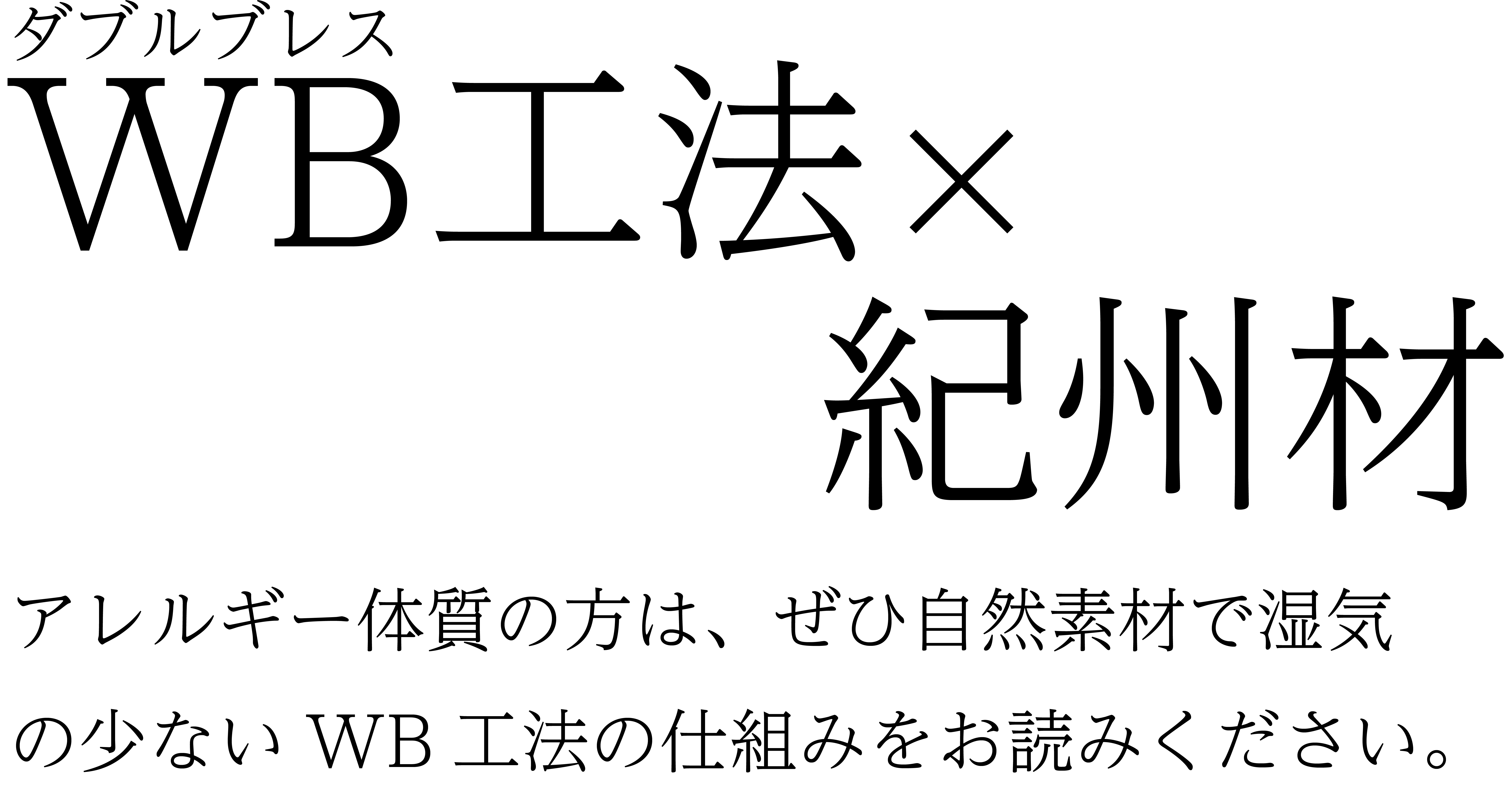
WB工法ワンポイント講座!
壁体内の上昇気流がゆっくりと床下の空気を引き上げ、それに引かれて外気がゆっくりと床下に入って来て、床下の空気と混ざります。
床下の空気は夏は涼しく、冬は暖かいです。
特殊な発煙管で実験したところ、空気と同じ比重の煙を模型の床下に入れますと温められて壁の中の空気がゆっくりですが上昇して、
床下の白煙を引き上げ、棟の開口部から屋外に流れ出るのを確認して頂けます。
夏場住宅は、屋根、小屋裏、2階、1階、床下と順次温度が低くなり、暖められた壁体内の空気は比重が軽くなって、ゆっくりと上昇します。
通気工法と聞くと、冬は寒いのでは?と心配される方もいらっしゃると思いますが、冬は各通気口が形状記憶合金により、自然に閉じて、家全体を空気の層でくるみます。
冷たい外気をしっかりガードして、室内の冷え込みを防ぎます。
また、業界最高クラス断熱性能(0.019W/m・K)を有する断熱材フェノバボードを標準仕様にしています。
熱的にも化学的にも安定したフェノール樹脂と非フロンガスを採用しており断熱性能の経年劣化も少ない優れた断熱材です。
断熱性能については断熱等級6の認定され十分な断熱性能を確保していますので、ご安心くださいね。


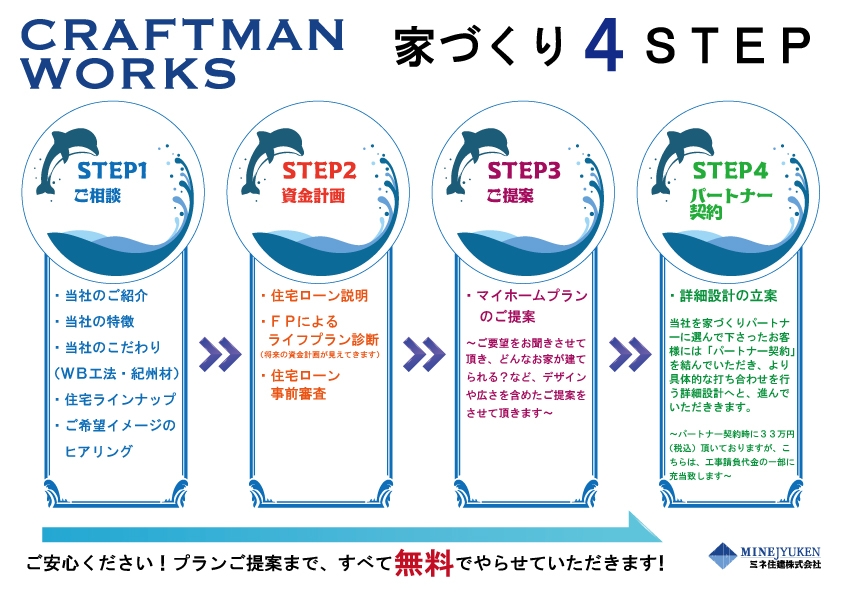
 ⾼耐震構造と呼ばれるモノコック構造の「真壁パネル工法」、「HSSピン工法」、家の耐久性と人の健康を守る「WB工法」、無垢材などなど
⾼耐震構造と呼ばれるモノコック構造の「真壁パネル工法」、「HSSピン工法」、家の耐久性と人の健康を守る「WB工法」、無垢材などなど 耐震等級3、断熱等級5以上を標準採用し、高耐震、断熱性な人と地球にやさしい家づくりをおこなっています。
耐震等級3、断熱等級5以上を標準採用し、高耐震、断熱性な人と地球にやさしい家づくりをおこなっています。